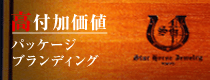通常の枡の中で最大の一升枡(容量約1.8ℓ)。
こんなに大きな枡はどのような歴史と用途があるのでしょうか?
歴史について
元々の単位である「合」が古来中国、漢の時代に決まり、日本に伝来して
から各地で大きさがバラバラだったのを徳川幕府が大きさを全国統一しました。
「量る」という概念は飛鳥時代頃に始まったとされます。
生まれが約1300年前、規格統一されたのが約400年前ということになります。
赤ちゃんに一升の米!?
赤ちゃんが1歳の誕生日に一升の米を背負わせるという
お祝い行事があります。
これには意味があります。
よくここまで育ちましたね、というお祝いと、「一升(一生)食うに困らない」
という願掛けです。
今の時代ですと1歳の子に約1.5㎏のお米を背負わせるなど虐待か!となりますが、
子供の成長と将来の食い扶持を祈っての行事なので、赤ちゃんが泣いても行うようです。
用途
言わずと知れた計量ですね。
お米の量、豆の量など特に穀物。
お酒や醤油もそうでしょうが、枡の痛みが早かったのではないかと。
塗装していないとすぐにダメになってしまいます。
漆でも塗っていたのかもしれませんね。
現代では節分の豆まきに主たる用途を移しています。
飾ったり、小物入れにしたりいろいろと使えますが、
弊社ではオリジナルの「スーパーポリマーコーティング」という
塗装(含浸系)をすることで料理やかき氷、丼にとお使いいただいています。
ちなみにオプション加工になります。
我が家では届いたはがき、封筒、書類を入れたり、細々したものを入れています。
案外便利です。
宝くじを入れておくと当たる確率が上がるかもしれません…知らんけど
DIYに自信のある方は高さをカットして、ウレタン塗装して皿代わりにも
お使いいただけます。
節分の豆まきになぜ枡を使うのか?
枡は年貢など計量器具でしたが、その役割が神を代行する呪物(縁起物)とされ、
特に枡の内側は異世界(入れたものに福を宿す)と言われてきました。
つまり枡に豆を入れて神の力を宿させ、これで厄を払うということですね。
神の役割を果たす枡。
これを知った日には枡をぞんざいに扱えないですし、弊社では職人が
気合入れて作っています!
素材
昔は杉で出来ていたようです。
いつの時代からか「神の木」といわれるヒノキがメインになりました。
今日は一升枡を取り上げてみました。
〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓
◇◆株式会社マル仁◆◇
住所 〒489-0977愛知県瀬戸市坂上町303-4
Tel 0561-21-8304 Fax 0561-83-2289
営業時間9:00~17:30(土曜日は12時まで)
定休日日曜、祭日 (土曜日 不定期休み)
〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓